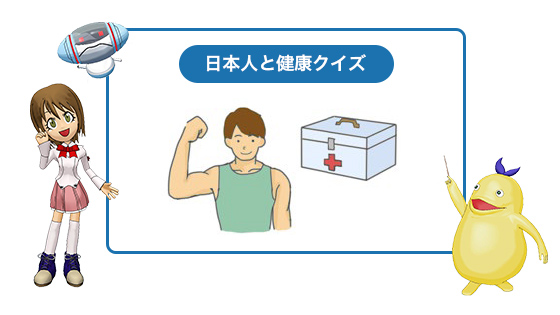第16課説明する - けが・病気 -
見てみよう
健康法
動画を見る
写真解説
クリック(タップ)で拡大と解説を表示します。
 ジョギング
ジョギング
いろいろな人たちが、健康のために、運動したり、工夫したりしています。ジョギングは人気が高い健康法です。 ストレッチ
ストレッチ
ストレッチや体操をする人もいます。体がやわらかくなって、けがの予防になります。 ラジオ体操
ラジオ体操
日本には「ラジオ体操」という体操があります。ラジオから流れる音楽やかけ声に合わせて体操をします。夏休みには、子供たちが毎朝、決まった公園に集まって、一緒にラジオ体操をします。 乾布摩擦・青竹ふみ
乾布摩擦・青竹ふみ
日本の健康法で、誰でも簡単にできるものを紹介します。乾布摩擦と青竹ふみです。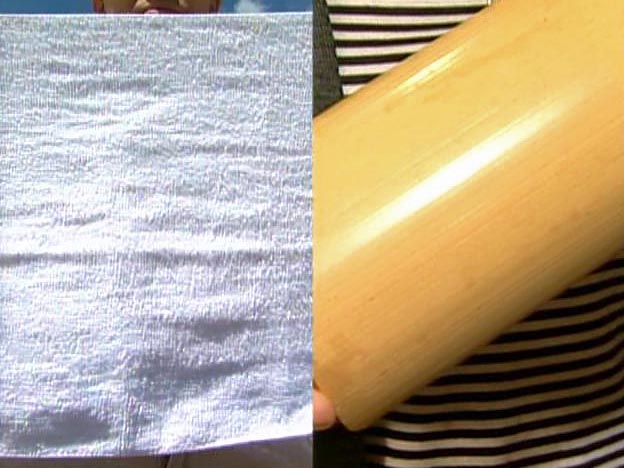 タオル・青竹
タオル・青竹
乾いたタオルや半分に割った竹を使う健康法です。 幼稚園1
幼稚園1
幼稚園です。日本では小学校に入る前に、幼稚園へ行きます。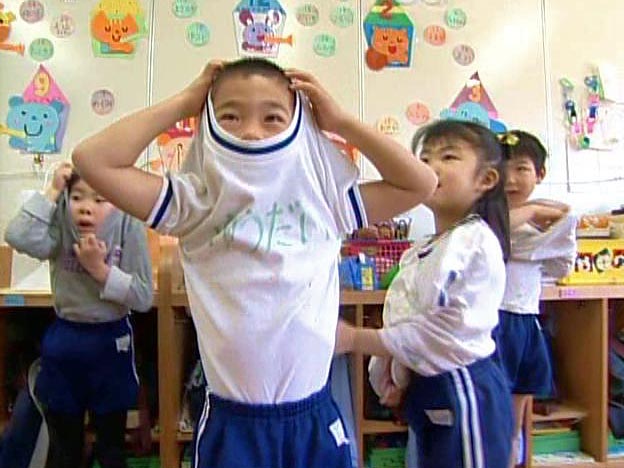 幼稚園2
幼稚園2
この幼稚園では昔ながらの健康法を取り入れています。 外に出る
外に出る
体操ズボンをはき、上半身ははだかのまま、タオルを持って外へ出ます。 庭で並ぶ
庭で並ぶ
幼稚園の庭です。クラスごとに並んで、大きな声でかけ声を出しています。 背中をこする1
背中をこする1
乾布摩擦をしています。乾いたタオルや布を使って、体をこすります。 背中をこする2
背中をこする2
先生を見ながら、みんないっしょに元気よく乾布摩擦をしています。 手をこする
手をこする
背中をこすってから、肩や手もこすります。今の気温は10度くらいですが、みんな元気です。 先生
先生
佐竹まゆ先生です。体をこすることによって、とてもあったかくなり、ひふもじょうぶになるので、かぜをひかない体になると思うと話しています。 池山珠子さん1
池山珠子さん1
池山珠子さんです。池山さんの健康法を教えてもらいます。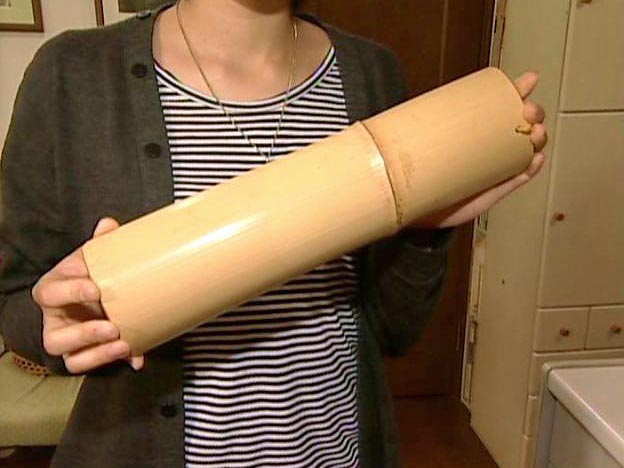 青竹1
青竹1
池山さんは青竹を使った健康法をしています。 青竹2
青竹2
青竹は竹で作られています。本物の竹でできているもののほかに、プラスチックなどでできているものもあります。 青竹ふみ1
青竹ふみ1
方法はかんたんです。青竹の上で、足ぶみをします。足のうらをしげきすると、血の流れがよくなります。池山さんは、中学生のとき、この青竹ふみを始めました。 池山珠子さん2
池山珠子さん2
高校受験の15歳くらいのときに、机にむかうことが多かったので、肩がこって、なんとかならないかと思い青竹を始めました。体の疲れがとれてリラックスできるのがいいところだそうです。 池山珠子さん3
池山珠子さん3
毎日15分ぐらいひまな時間をみつけて、青竹ふみを続けています。 いろいろなふみ方
いろいろなふみ方
青竹ふみにはいろいろなふみ方があります。つちふまずを青竹の端の部分にあわせてふんだり、動かしながら押し付けたりします。 片足でふむ1
片足でふむ1
片足だけで立って体重をかけます。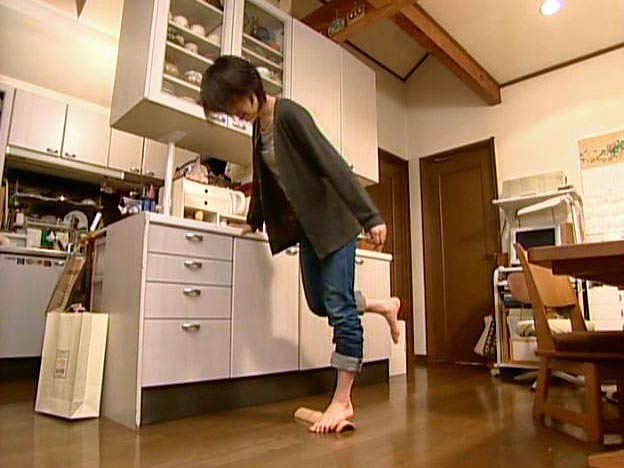 片足でふむ2
片足でふむ2
何かにつかまると、片足でも体を前に傾けたりして、足の裏のいろいろな部分を刺激することができます。ちょっといたいぐらいが気持ちよくて、「いたきもちいい」と池山さんは言っています。 乾布摩擦
乾布摩擦
こどもたちも、先生も乾布摩擦を楽しく元気にやっています。誰でもできる日本の健康法です。 青竹ふみ2
青竹ふみ2
青竹ふみも、簡単にできる日本の健康法です。